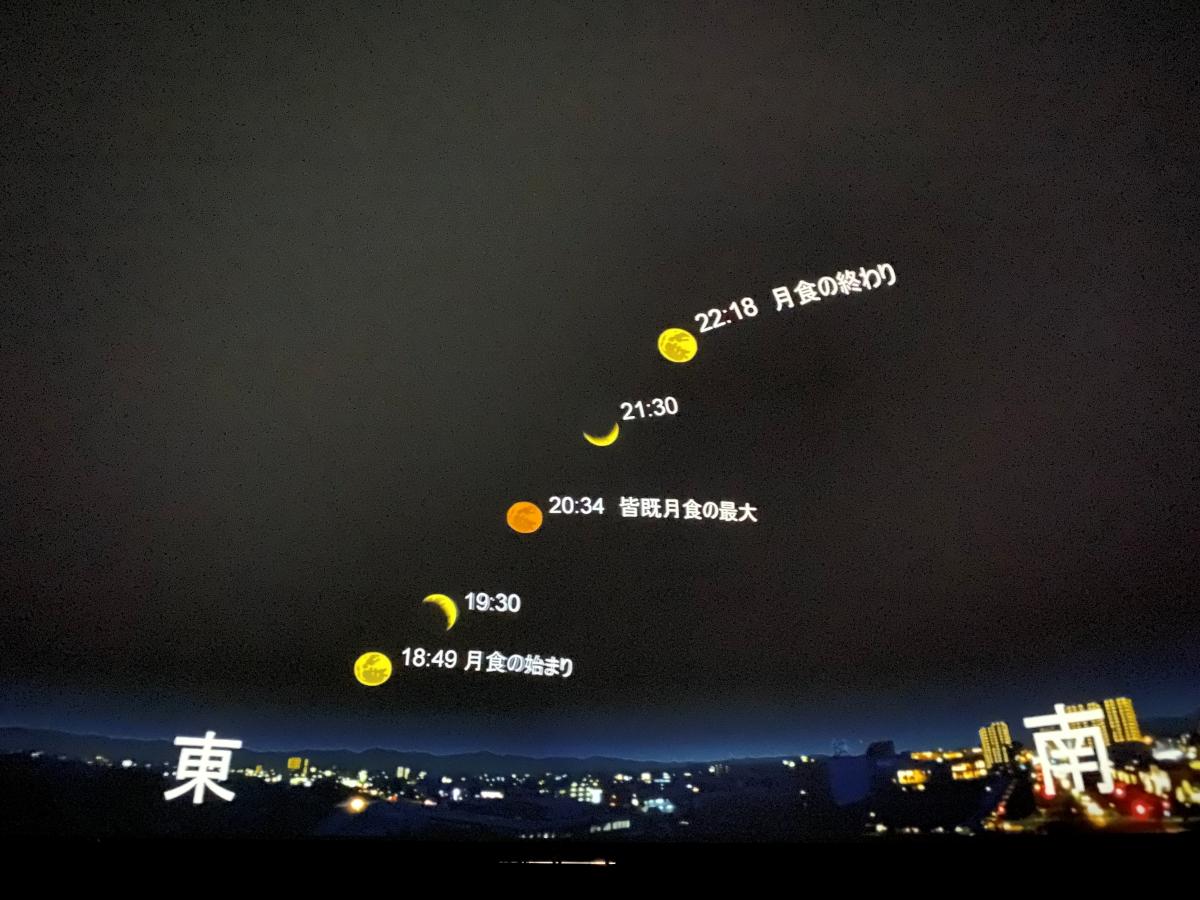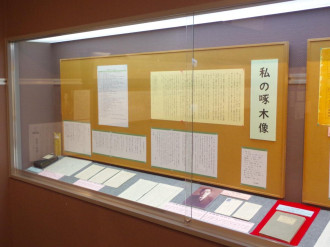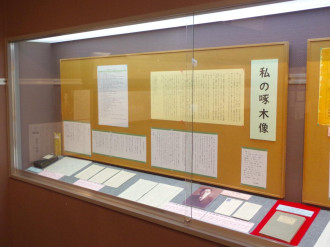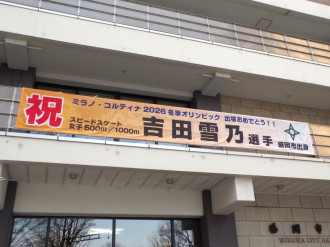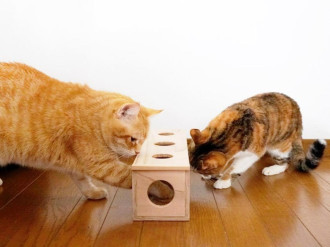【連載】盛岡の「なんかいい」話Vol.3 盛岡を考える人<後編・佐藤俊治さん>
盛岡に本社を構え新しい文化を世界に発信する「ヘラルボニー」で広報を担当する矢野智美さん。
出身地の群馬県から盛岡に移住し、まもなく10年がたとうとしています。
「盛岡愛」が加速する中で感じているのは、「盛岡は、なんだか心地いい」という思い。
この「なんかいい」には理由があるはず。
「なんかいい」の理由を探るために、
矢野さんは「盛岡を愛する人の視点」から盛岡の街を見てみようと、
さまざまな立場で盛岡を愛する人に会いに行くことにしました。
この連載では盛岡を愛する人の話を聞きながら、盛岡の「なんかいい」を探ります。
「今の盛岡をつくる人の声が聞きたい」と矢野さんが会いに行ったのは、盛岡市役所で働く佐藤俊治さん。うわさでは「会った人を盛岡ファンにしてしまう」ほどの盛岡好きだとか。愛を持って今の盛岡に携わる佐藤さんに話を聞きました。
【プロフィール】
矢野智美さん(左):群馬県生まれ。2015(平成27)年、岩手県のテレビ局にアナウンサーとして入社。盛岡に移住して今年で10年目。現在は「ヘラルボニー」の広報として「岩手から新しい文化の発信」を目指し、同社の活動や取り組みを発信する仕事を担う。
佐藤俊治さん(右):盛岡市経済企画課所属(※2024年11月当時。現在は他部署に異動)。現在は商店街の活性化などの仕事に関わる。盛岡好き市職員として知られ、休日にはさまざまな地域イベントで姿を見かけることも。佐藤さんをきっかけに盛岡好きになる人も多い。
-矢野さんが市職員の方から話が聞きたいと思ったきっかけは一冊の本でしたね。
矢野:そうなんです。元盛岡市職員の佐藤優さんが書いた「脈脈 盛岡の街づくり」という本です。この本を通して自然、歴史といった「盛岡」らしさを軸に街づくりの最前線で汗を流した方の思いを知りました。まちづくりの根拠になる数字や、当時の美しい街並みの写真を見て「盛岡の街は人の手によって守られてきたんだな」と感じました。「盛岡ってなんだか居心地がいいな」と感じる理由を探し始めたのも、この本を読んでからです。
佐藤:本当ですか。私もその本を読みましたよ。1984(昭和59)年に出版されていますが、「この時代にこの本が書けるのか」と驚きましたし、全く古さを感じさせない内容でした。著者の佐藤優さんにお会いしたことはありませんが、尊敬している市職員の一人です。
矢野:私の個人的なイメージですが、市職員の皆さん一人一人の個性や仕事が見えづらくて、「市の人」という一つの塊で捉えていました。「脈脈 盛岡の街づくり」を読んでから著者の「盛岡愛」が伝わってきて、こんなに盛岡を愛して仕事をしている職員がいるんだと思いました。それから同じく盛岡に対して愛情や独自の視点を持っている職員の方と話してみたいと考えていたんです。
-佐藤さんはこれまで市役所でどのような仕事に関わって来たんですか?
佐藤:最初に配属されたのは医療費助成に関連する窓口、それから農業委員会、企画調整課、地域福祉課、都市戦略室と異動してきました。現在は経済企画課(※2024年11月当時。現在は他部署に異動)という部署で中心市街地や商店街の振興に関わっています。
矢野:佐藤さんと以前お話しした時に「自分は市役所職員として多数派ではない」と言っていたのが印象的でした。どういうところが多数派ではないと思っていたんですか?
佐藤:私は秋田出身で、大学は福島だったので、盛岡出身ではなく、大学も岩手ではないという所が多数派ではないということですね。仕方ないことだと思いますが、市に入った頃は何となく外様感を持っていました。今は盛岡のことが好きですが、盛岡に全く興味がない時期もありました。
矢野:えっ、そうなんですか?
 佐藤:はい。盛岡に来て友人も知人もいなくて、学生時代を過ごした福島の方が楽しかったなと感じていました。地域福祉課に異動した年に東日本大震災が発生して、震災関連業務に関わる中で、みんなで何かできないかと活動する場にプライベートでも参加するようになり、盛岡の皆さんと知り合い、仲が深まったように思います。さまざまな部署の業務を通じて地域の人と関わり、盛岡の街自体に興味を持つようになりました。
佐藤:はい。盛岡に来て友人も知人もいなくて、学生時代を過ごした福島の方が楽しかったなと感じていました。地域福祉課に異動した年に東日本大震災が発生して、震災関連業務に関わる中で、みんなで何かできないかと活動する場にプライベートでも参加するようになり、盛岡の皆さんと知り合い、仲が深まったように思います。さまざまな部署の業務を通じて地域の人と関わり、盛岡の街自体に興味を持つようになりました。
矢野:盛岡を好きになるきっかけは何だったんですか?
佐藤:実は市民から「市の職員なのに、こんなことも知らないなんて」とお叱りを受けることがあり、それがきっかけで「もりけん(盛岡もの識(し)り検定)(※)」を受験しました。それ以外でも、市民と関わる場面でもっと盛岡の知識を身に付けなくてはと思ったことがあります。盛岡について勉強するうちに盛岡の歴史や地域に根付く文化の深さを知って、そこから盛岡が好きになりました。
(※ 盛岡もの識り検定=盛岡商工会議所が主催する、盛岡市に関する歴史、文化、風土など多分野にわたり、『盛岡通』度を認定する検定試験。通称、もりけん。3級~1級がある)
矢野:もともと盛岡が好きではなかったという所は私も共感できます。私はアナウンサーとして就職したので、仕事上、盛岡をはじめ岩手全体のことを知る必要がありました。その過程があったからこそ、今とても盛岡が好きなのかなと思います。
佐藤:私は盛岡の知識を学ぶところから好きになったので、逆に盛岡についてよく知らないまま好きになっていく人のことがすごいなと思います。「盛岡はなんとなく良いよね」と言う人が多くいますが、その「なんとなく良いよね」という感覚が分からないんです。そう感じるきっかけをぜひ聞いてみたいですね。
-実は、「佐藤さんは人を盛岡ファンにする達人だ」といううわさを聞いたのですが…。
佐藤:それは私個人が取り組んでいる社会実験のことですね。県外から盛岡を訪れる人を十二分にもてなし、その人が好きそうな場所に連れて行って、盛岡を好きになってもらい、最終的には盛岡に移住させるという…(笑)
矢野:結果が出るまでに長い時間がかかる実験ですね。…実際に移住した人はいるんですか?
佐藤:移住する人はまだいません(笑) ただ、盛岡に関わってくれる「関係人口」は増やせました。
関係人口という点では、都市戦略室時代に移住・定住に関連する業務や、盛岡の関係人口を増やすためのプロジェクト「盛岡という星で」の立ち上げにも携わりました。
矢野:異動する部署ごとに全く違う分野の仕事をしていますよね。大変ではないですか?
佐藤:確かに、部署によって業務の内容や必要な知識が変わるので大変です。盛岡の街に対するアプローチはそれぞれで違うのですが、最後は共通する何かにつながっていると感じます。農業も福祉も移住定住も、どの分野にも街の魅力や価値につながる入り口が必ずあるんです。部署を異動する度に新しい入り口が見つかります。
矢野:部署が変わる度に新しい視点から盛岡という舞台を見てきたんですね。
佐藤:そうですね。今の経済企画課では、商いを営む側から盛岡の街が作られている視点を学んでいます。例えば、「盛岡信用金庫」さんや「ござ九」さんはいわゆる歴史的建造物で、現在も営業を続けられています。事業者がなりわいを続けることで街が守られている状態は尊いことです。個人的には事業者が希望を持って商売を続けられるような取り組みと盛岡の魅力につながる取り組みを組み合わせた施策を考えていけたらいいなと思っています。
矢野:ヘラルボニーの本社が入居しているビルも独特の構造をしていて、「おしゃれな建物だね」と言われることがあり、私もとても気に入っています。もしもこのビルから全てのテナントがいなくなってしまったら、ビル自体がなくなるかもしれないと考えると、入居しているだけで街並みを守っているとも考えられますね。
佐藤:矢野さんのその考え方のように、ただ商売しているだけではなく何らかの形で街に魅力や価値を提供している事業者が盛岡には多いですよね。景観を守るために行政を頼るのではなく、自分たちの商いで守っている。そういう人たちをもっと評価するべきだと思います。
-佐藤さんは先ほど「なんとなく良いよね」が分からないとも言っていましたが、この連載では「盛岡ってなんだか居心地がいい」と感じる理由、「なんかいい」の理由を探しています。佐藤さんが「盛岡ってなんかいいな」と思うところって、どんなところでしょうか?
佐藤:そうですね…今のところ「私も『盛岡のなんかいいな』が分かると良いな」という感じです。盛岡の良さって特化したものがないところだと思います。一つ一つの光は強くないけど、光るものがたくさんあるのが盛岡の良さだと思いますが、プロモーションする側としては何かた尖(とが)ったものを一つアピールしたいと思うので、「一押し」に振り切りづらい盛岡はプロモーションがやりづらい街だろうなと思います。
矢野:例えば香川県の「うどん県」のような、分かりやすい売り出し方は難しいってことですか?
佐藤:そうそう。でも盛岡は、たくさんある光の中で「私はこれが好きだ」と言える街、その人にとって一個だけ刺さるものがある街で良いんじゃないかなって思います。
矢野:それだけたくさんの彩りが混じり合って結果的に盛岡ができているってことですね。
佐藤:あと、私は「まちづくり」という言葉があまり好きではなくて、最終的に「街は作られるもの」だと捉えています。「街」はそこに暮らす人のやりたいことの集合体で、その人たちが作ろうと思ったものが混じり合った結果ではないでしょうか。そういう熱量を持つ人たちが作った街だから盛岡が好きなのかもしれません。
矢野:なるほど。市の皆さんが土台を作っていて、私たちのような民間企業や市民個人の集合体が街を作っているという見方がとても面白いです。私たちも「こういう街にしたい」というビジョンは持っていますが、全部を押し付けたいわけじゃない。一滴だけ染みだして、街が変化する手伝いができればと思っています。
佐藤:ここまで話しましたが、「なんかいい」はやっぱり分かりません…。私は盛岡の良さを知識として知ってしまったので、全部伝えたいんです。市外から来た人と街を歩いていると、聞かれてもいないのに歴史や建物について解説してしまいます。「なんかいい」を感覚で捉える方法が知りたいです(笑)
矢野:佐藤さんは感覚と知識をしっかり結び付けて認識しているタイプなんですね。「なんかいい」という目に見えない事象についてもきちんと説明してほしいという感じですか?
佐藤:おっしゃる通りです。盛岡の「なんかいい」と感じる部分は全部言葉にできると思っていますが、一人一人感じている部分が違うのでそれぞれの言語化が難しいのかもしれません。
-知識から知った盛岡の良さが仕事で生かされる場面ってありますか?
佐藤:知識は市民の皆さんとのコミュニケーションに役立ちます。矢野さんも言っていましたが、私たち市職員は「市役所の人」というひとくくりで見られがちです。盛岡で昔何があったのか、今何が起きているのかを知らないと、「市の人なのに何も知らないんだ」とコミュニケーションを遮断されてしまうこともあります。知識があれば、「よく知っているな」と話題を広げたり、掘り下げたりすることもできます。
 矢野:佐藤さんのことを助けてくれるのが、盛岡を好きになるきっかけだった知識なんですね。
矢野:佐藤さんのことを助けてくれるのが、盛岡を好きになるきっかけだった知識なんですね。
佐藤:私が持っているのはまだまだ浅い知識です。盛岡の各地域にはその場所を深く知る人たちがたくさんいて、そういう人とコミュニケーションを取る時、浅い知識でも身に付けておけば役に立ちます。
矢野:盛岡の面白いところは、歴史を知る人に街で出会えることですよね。私も喫茶店を訪れた時、「昔はこんなことがあった」という話が聞こえてくると、ついつい聞き耳を立てています。
佐藤:本当にその通りで、私も市民の皆さんと話すことで、私が知らない盛岡に触れるのが面白いです。パズルのピースが埋まるような気持ちになります。
矢野:盛岡の「なんかいい」理由を見つける方法の一つは、「盛岡を知識として学び、自分の言葉で伝えること」だと気づきました。今日はありがとうございました。
前編はこちら
Vol.3 盛岡を考える人<前編・高橋真菜さん>
盛岡の「なんかいい」話Vol.1はこちら
Vol.1 盛岡に暮らす人<前編・浅沼宏一さん>
Vol.1 盛岡に暮らす人<後編・伊藤隆宗さん>
盛岡の「なんかいい」話Vol.2はこちら
Vol.2 盛岡を伝える人<前編・山影峻矢さん>
Vol.2 盛岡を伝える人<後編・玉木春香さん、知念侑希さん>