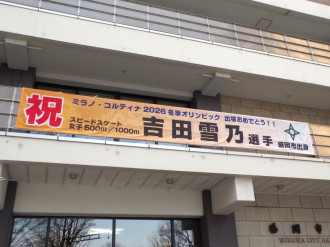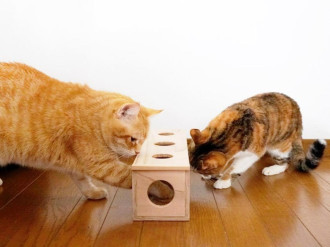【連載】盛岡の「なんかいい」話 Vol.3 盛岡を考える人<前編・高橋真菜さん>
盛岡に本社を構え新しい文化を世界に発信する「ヘラルボニー」で広報を担当する矢野智美さん。
出身地の群馬県から盛岡に移住し、まもなく10年がたとうとしています。
「盛岡愛」が加速する中で感じているのは、「盛岡は、なんだか心地いい」という思い。
この「なんかいい」には理由があるはず。
「なんかいい」の理由を探るために、
矢野さんは「盛岡を愛する人の視点」から盛岡の街を見てみようと、
さまざまな立場で盛岡を愛する人に会いに行くことにしました。
この連載では盛岡を愛する人の話を聞きながら、盛岡の「なんかいい」を探ります。
「コーヒーの街」とも呼ばれる盛岡には、老舗から若者が始めた新しい店までたくさんのコーヒー店があります。街を漂うコーヒーの香りは、地域の景観を生み出す要素になっているといっても過言ではありません。多くの市民から愛される「クラムボン」もその店の一つです。店主の高橋真菜さんにコーヒーとまちづくりについて聞きました。

【プロフィール】
矢野智美さん(右):群馬県生まれ。2015(平成27)年、岩手県のテレビ局にアナウンサーとして入社。盛岡に移住して今年で10年目。現在は「ヘラルボニー」の広報として「岩手から新しい文化の発信」を目指し、同社の活動や取り組みを発信する仕事を担う。
高橋真菜さん:自家焙煎(ばいせん)コーヒー店「クラムボン」の店主。2019(平成31)年1月に亡くなった先代店主の父・正明さんに代わって店を引き継いだ。朝晩には真菜さんが焙煎するコーヒー豆の香りが街を包む。幼い頃から紺屋町で長い時間を過ごし、現在は「紺屋町まちづくりの会」のメンバーとして、紺屋町の景観を守る活動にも加わる。
-店内が香ばしい香りでいっぱいですね。コーヒー豆の焙煎中ですか?
高橋:そうなんです。この香り、大丈夫ですか? 結構強いので、服や髪についてしまって、家族からは「焦げ臭い」って言われることもあります。私は慣れてしまっていて分からないんですが…。
けむくないですか?
矢野:とんでもない。むしろ好きな香りです。店の前を通るといつも焙煎中の良い香りがして、「どんな店だろう?」と気になっていました。店内は落ち着いていて歴史を感じますね。店はいつ、始められたのですか?
高橋:この店は1989(平成元)年からです。父がやっていた前身の店があって、それを含めると50年くらいになります。
-先代の店主で父親の正明さんが2019(平成31)年に病気で亡くなって、その後、真菜さんがこの店を?
高橋:はい。大学卒業後から店を手伝い始めて、焙煎から接客まで1人でこなすようになったのは2年ほど前からです。手伝い始めた頃は店を継ぐということは考えていなくて、父のことも、家族のことも、店のことも好きで、父を手伝いたいという気持ちがありました。
矢野:もしかして、大学でコーヒーや店に関わる勉強をされて、店を手伝うようになったんですか?
高橋:いえ、全く別な分野でした。県外の大学に進学しましたが、もともと盛岡に戻ろうと決めていて、勉強したこと以外を仕事にするなら、この店だろうと考えていました。
矢野:本格的に店を引き継いでいこうと考えたきっかけはありますか?
高橋:そうですね…意識が大きく変わったのは、父から焙煎を教わったころだと思います。10年ほど前に父に「焙煎やってみるか?」と言われて。私も興味があったので「ぜひ」と答えたんです。父は焙煎を人に教えるつもりはなかったみたいですが、私には教えてもいいって思ってくれたみたいです。
-焙煎を教わったころには真菜さんが店を継ぐことは決まっていたんでしょうか。
高橋:その頃は、これからの焙煎は父と私で手分けしようと話していました。あくまでも父がトップで、私はサポート。でも、学べば学ぶほど「父の味を絶対に残したい」という気持ちは強くなっていましたね。「私がやるんだ」と心を決めたのは、父の病気が分かってからです。
矢野:お父さんが闘病されていた間も、焙煎について何かアドバイスをもらっていたんですか?
高橋:私がメモにまとめておいて、それを聞くような形でしたね。父は優しい人だったので、私が相談しても「大丈夫だよ」としか言わなくて。でも、そんな風に任せてくれたおかげで、自分の好きなように学べたんだと思います。(タイマーが鳴る音)…ちょっと、豆の様子を見てきますね。
矢野:焙煎の様子を見てもいいですか?
高橋:もちろん。焙煎自体はもうすぐ終わるところで、このあとは豆を冷やしていきます。
矢野:大きくて立派な焙煎機ですね。わぁ、近づくと温かい! 焙煎する時の温度や時間は決まっていますか? それとも感覚ですか?
高橋:今は温度計を付けて計測していますが、父は感覚でした。教わった時は温度や時間は数値化も言語化もされていなくて、マニュアルもありません。良くも悪くも昔の職人らしいというか…父は手で釜を触った温度や、豆が弾ける音で判断していたみたいです。
矢野:えー! この熱々の釜を直接手で触るんですか?
高橋:そうですよ、びっくりしますよね(笑) 父が豆の様子を見て、「これくらいで大丈夫だから」と言うんですが、私は全く分からなくて一時期とても悩んでいました。
矢野:真菜さんは今もお父さんのコーヒーの味を守り続けていますよね。少し意地悪な質問だったらすみません。店を引き継いだ今、お父さんの味ではなく自分の味を出そうとは思いませんか?
 高橋:実は、その質問されることが多いんです。私の中には、自分の味を出したいという気持ちの前に、父が作ったものを残したいという思いが強くあります。ただ全く同じでは駄目なので、父の味を絶対に守った上で、今の自分が持つ技術できることをプラスしています。父がいた時代には扱っていなかった新しい豆も入れました。その選び方も、父が好きそうだなとか、常連さんが好きそうだなという視点で選んでいます。
高橋:実は、その質問されることが多いんです。私の中には、自分の味を出したいという気持ちの前に、父が作ったものを残したいという思いが強くあります。ただ全く同じでは駄目なので、父の味を絶対に守った上で、今の自分が持つ技術できることをプラスしています。父がいた時代には扱っていなかった新しい豆も入れました。その選び方も、父が好きそうだなとか、常連さんが好きそうだなという視点で選んでいます。
-話は変わりますが、真菜さんは幼い頃から紺屋町で過ごしているとのこと。真菜さんにとって紺屋町はどんな場所ですか?
高橋:とにかく川ですよね。子どもの頃はずっと中津川で遊んでいました。盛岡が好きな理由として真っ先に思い浮かぶのが、紺屋町と中津川周辺のエリア。それくらい中津川はマストな存在になっています。
矢野:紺屋町は川でつながっているエリアですよね。店や住居が長屋のように連なっていて、その裏には川が流れて、川と密接な酒蔵や染物屋がある。盛岡の中で一番盛岡らしさを感じられるエリアのような気がします。
高橋:分かります。歴史的な要素が残りつつ、川沿いに個性的な個人店が並んでいて、その真ん中にデーンと川が流れる。この風景が小さい頃から大好きです。
矢野:同じ歴史的な要素が残る地域でも、紺屋町と鉈屋町では街のつくりが違いますよね。
高橋:それぞれ特色がありますよね。鉈屋町も大好きなエリアです。あと、肴町も。高校生の頃は肴町が遊び場でした。バスセンター側の入り口の角に昔はマクドナルドがあって…。
-懐かしい。私も子どもの頃に家族と中三に行き、帰りはマクドナルドに寄ってもらっていました。
高橋:そうそう、中三! 懐かしいな。女子高生は皆であそこのマックに行って、プリクラを撮っていましたね。
矢野:当時の若者にとって肴町は、現在の大通り商店街のような存在だったんですね。今はなくなった風景の話題になりましたが、紺屋町では昔ながらの店や酒蔵がなくなり、マンションなど新しい建物の建築が進んでいます。そういった地域の変化についてはどう感じていますか?
高橋:小さい頃から当たり前だった風景がなくなるなんて想像できなかった、という気持ちです。家族や友人や恋人を失うのとは違う感覚で、悲しいし、寂しい。でも、街の変化を止める権利は私にはない。このまま失われていくのは良いんだろうか、これまでの風景を守りたくても私一人では何もできないと考え、無力感がありました。
-真菜さんは現在、紺屋町の景観を守る方法や未来について考える「紺屋町まちづくりの会」のメンバーとしても活動されていますね。この会ができるきっかけについてお聞きしていいですか?
高橋:「菊の司」さんの跡地にマンションができると決まった頃に、普段から交流がある店の皆さんが「大丈夫?」とここを尋ねてくることが増えました。これまで街のことについて話す機会はなかったのですが、その頃から積極的に街について言葉を交わすようになり、「このままでは駄目だね」とみんなで集まるようになったんです。
矢野 真菜さんも他の皆さんも「紺屋町を守らなくては」「今後のまちづくりのために何かアクションを起こそう」と動き始めたんでしょうか?
高橋:そ うですね。最初はマンションに対する提案から始まって、今は同じようなことが起きた時に街を守るために何かしらの決まりを設けることができないかとみんなで考える方向に向かっています。街や景観に対する思いや考えは人それぞれで、私たちだけで決めることはできません。たくさんの人から話を聞きつつ、市役所の皆さんも協力してくれています。
うですね。最初はマンションに対する提案から始まって、今は同じようなことが起きた時に街を守るために何かしらの決まりを設けることができないかとみんなで考える方向に向かっています。街や景観に対する思いや考えは人それぞれで、私たちだけで決めることはできません。たくさんの人から話を聞きつつ、市役所の皆さんも協力してくれています。
-「紺屋町まちづくりの会」の皆さんは、新しく建つものに反対したり、新しく住む人を追い出したりしたいのではなく、互いに上手に付き合いたいという思いで活動していますよね。
高橋:そうなんです。私たちもその思いがあまり伝わっていないなと感じています。マンション反対や建設中止を訴える活動をするために会を立ち上げたわけではありませんし、新たな住人となる皆さんとは仲良くしたいです。うまくやりながら、一緒に紺屋町らしさを守っていきませんか、と言うのを伝えたいです。
矢野:真菜さんは「お父さんの味とこの店を守りたい」という気持ちを持っていますが、店を続けるためには、新しい住人の皆さんとも良い関係を続ける必要がありそうですね。
高橋:はい。新しいものを受け入れつつ、共存していきたいというのが私たちの思いです。昔から紺屋町で商売してきた人がこれからもこの場所で続けられるように提案しています。
-昔からの住人も、新しい住人も、互いに居心地の良い環境を作って行こうという動きですよね。さて。この連載では「盛岡ってなんだか居心地がいい」と感じる理由、「なんかいい」の理由を探しています。真菜さんが「盛岡ってなんかいいな」と思うところって、どんなところでしょうか?
高橋:「なんかいい」…なんと言えばいいですかね、温度感と言うんでしょうか。人も街も基本は温かくて、優しいけど、それぞれが「個」を持っている。一人でもやっていけるけど、ちゃんと周りにいてくれて、寄り添ってくれるというか。
 矢野:とっても分かります。その温度感。一人でいる時間を大切にすることもできるし、何かあった時には「大丈夫?」と声をかけて助けてくれることもありますよね。
矢野:とっても分かります。その温度感。一人でいる時間を大切にすることもできるし、何かあった時には「大丈夫?」と声をかけて助けてくれることもありますよね。
高橋:そうなんです。一人になりたい時には一人でいさせてくれるし、誰かが必要な時はすぐに温かく寄り添ってくれる。そういう温度感を小さい頃から感じています。
矢野:温度感って盛岡の街を説明するのにちょうど良い言葉ですね。寄り添ってくれるぽかぽかした温かさも、そっとしてくれる少しクールなところも、「盛岡は温度感のある街」だと改めて感じました。
高橋:あと、これは長所と短所の両方の面があると思いますが…盛岡の人は「はっきり言わない」ところがありますよね。まちづくりに関わるようになり、いろいろな人と言葉と交わす中で、一人一人がしっかり考えを持っていて、熱い思いを持っていることが分かりました。同時に、「これまで言いづらかった」という言葉も聞いて、しっかり話す場も必要なのかなと思いました。
矢野:「遠慮がち」というのは奥ゆかしさもあって盛岡らしさの一つとして挙げられることがありますが、大切なものを守るために勇気を出してはっきり言葉に出さないといけない時もありますよね。真菜さんの視点で盛岡の街の話を聞いて、私の中の盛岡の輪郭がくっきりと見えた気がします。今日はありがとうございました。
後編はこちら
Vol.3 盛岡を考える人<後編・佐藤俊治さん>
盛岡の「なんかいい」話Vol.1はこちら
Vol.1 盛岡に暮らす人<前編・浅沼宏一さん>
Vol.1 盛岡に暮らす人<後編・伊藤隆宗さん>
盛岡の「なんかいい」話Vol.2はこちら
Vol.2 盛岡を伝える人<前編・山影峻矢さん>
Vol.2 盛岡を伝える人<後編・玉木春香さん、知念侑希さん>