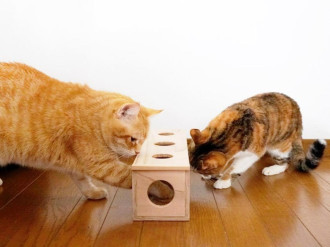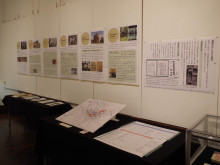【連載】盛岡の「なんかいい」話 Vol.1 盛岡に暮らす人<前編・浅沼宏一さん>
盛岡に本社を構え新しい文化を世界に発信する「ヘラルボニー」で広報を担当する矢野智美さん。
出身地の群馬県から盛岡に移住し、まもなく10年がたとうとしています。
「盛岡愛」が加速する中で感じているのは、「盛岡は、なんだか心地いい」という思い。
この「なんかいい」には理由があるはず。
「なんかいい」の理由を探るために、
矢野さんは「盛岡を愛する人の視点」から盛岡の街を見てみようと、
さまざまな立場で盛岡を愛する人に会いに行くことにしました。
この連載では盛岡を愛する人の話を聞きながら、盛岡の「なんかいい」を探ります。
「葺手町(ふきでちょう)商店街」は、旧町名の葺手町で呼ばれ、昔ながらの店と新しい店が混ざり合うエリアです。この場所で老舗しょうゆ店「浅沼醤油(しょうゆ)店」の4代目として、しょうゆをはじめとするさまざまな調味料を販売する「クラビヨリ」を営む浅沼宏一さんに話を聞きました。

【プロフィール】
矢野智美さん(左):群馬県生まれ。2015(平成27)年、岩手県のテレビ局にアナウンサーとして入社。
盛岡に移住して今年で10年目。現在は「ヘラルボニー」の広報として「岩手から新しい文化の発信」を目指し、
同社の活動や取り組みを発信する仕事を担う。
浅沼宏一さん(右):1914(大正3)年創業の浅沼醤油店の社長。
しょうゆやみそのほかに、岩手の食材を生かしたドレッシングやシロップなど独自の調味料も開発している。
しょうゆに関する研究にも取り組み、県内企業や同業者とのコラボレーションにも積極的。
商店街でのイベント企画にも携わる、地域の窓口的存在。
-「クラビヨリ」はもともと築200年を超える盛岡町家だったんですよね。
浅沼:はい。ここは2つの町家をくっつけた形になっていて、子どもの頃は「忍者屋敷だ!」なんて言って、よく走り回ったりかくれんぼしたりしていました(笑)。 私も、私の父と祖父も暮らした家です。
矢野:じゃあ、浅沼さんが育った家が店になっているんですね。盛岡町屋というと鉈屋町のイメージがあったので、ここのエリアにも町家があるとは思いませんでした。
浅沼:そうですね。もともとは生活の場だったのが、110年前にしょうゆ屋をやろうとなって商売を始めて、今に続くなりわいの場になりました。工場は郊外に移転していますが、昔はここにあったんですよ。工場が移転してからはたばこや塩の販売をしていた時期もありました。調味料のお店としてオープンしたのは2009(平成21)年です
矢野:店を見て回ると、一般的なしょうゆだけではなく、面白い調味料がたくさんありますね。県産の木材を使ったシロップや、規格外のパンを使ったしょうゆもあるんですか…しょうゆって一言に言ってもいろいろな種類や造り方があることに驚きました。
浅沼:実は、しょうゆには細かくて厳しい規格があるんです。安全で品質が高いものを提供するには規格を守ることが大切です。規格を設けることによって悪い製品が出回らなくなりました。ただ、良くも悪くも「外れがない」というか。各メーカーの個性が失われてしまった側面を感じています。
矢野:なるほど、そうなんですね。ちょっと違うかもしれませんが、実は私がアナウンサーだった頃、アナウンサーらしい読み方や、決められた時間通りに読むなど、「アナウンサーとして求められる規格」に合わせることが苦手でした。振り返るとアナウンサーとしては「規格外」だったのかもと思う節もあります。でも、今の仕事では、これまで規格外だった部分が自分の個性になっていると思えるようになりました。しょうゆの厳しい規格の中で、浅沼さんが規格外のものを使った商品づくりに挑戦しているのはなぜですか?
浅沼:規格を守ることと規格を外れることは両方必要だと思います。社会のルールに沿って稼ぐことは大事ですが、それだけが人生ではありません。規格の外に思うようにいかない物事の面白さを見つけて、そこに自分が持っている知恵やクリエーティブをちょっと乗せて、新しい発見ができた時の自分なりの喜びを誰かと分かち合うことも大切だと思います。この店は規格に合わせて作った商品と一緒に、自分がやりたい規格外のものを表現する場にしたいと思っています。
-2023年に店をリニューアルして、以前よりも町家の構造を生かす形になりましたね。
矢野:町家を生かすという点で難しいところはありましたか?
 浅沼:生かすというよりは、元に戻したというのが近いかもしれません。今は店の前の軒先にベンチを置いていますが、あの軒先はリニューアル前にはなくて、逆に直営店になる前にはありました。店内で買ったソフトクリームを家族で座って食べたり、散歩の途中で立ち寄った人が座って休んだり、店と地域のちょうど境目で公園みたいな場所になっています。自分で言うのもなんですが、われながら良い場所だなと。
浅沼:生かすというよりは、元に戻したというのが近いかもしれません。今は店の前の軒先にベンチを置いていますが、あの軒先はリニューアル前にはなくて、逆に直営店になる前にはありました。店内で買ったソフトクリームを家族で座って食べたり、散歩の途中で立ち寄った人が座って休んだり、店と地域のちょうど境目で公園みたいな場所になっています。自分で言うのもなんですが、われながら良い場所だなと。
矢野:そんな光景が広がっているとは、すてきですね! 商品を買った人だけが使うのではなく、誰でも利用できて、みんなが集まる場所になっていることで建物に新しい価値が生まれているようです。町家も喜んでくれそうですね。
浅沼:そうですね。店として使っていなかった軒先を今のように使ってもらえているのがうれしいです。暮らしていた家が時代に合わせて人の役に立っていることを、先祖の皆さんもこの家自体もきっと喜んでいることだろうと思っています。
-地域との関わりに話を移しますが、浅沼さんは葺手町商店街の皆さんで構成する「葺手町商店会」の窓口的存在ですよね。店主の皆さんや地域の皆さんと接する時に意識していることはありますか?
浅沼:自然体でいることかな。「商店街だからみんなで何かやらなきゃいけない」と縛るのではなく、何かひらめいた時に「ちょっと集まってやってみようか」みたいな感覚でゆるく付き合えているのが葺手町の良いところです。たった140メートルしかない商店街の中に、古い店と新しい店が混在していて、それぞれに個性があるので、商店会のみんなで集まって話すのも面白いですよ。
矢野:確かに。葺手町は他の地域とちょっと世界観が違いますよね。石畳の路面や街灯のデザインもかわいくて。私にとっての葺手町はおいしいものがあるエリアで、ランチやカフェタイムで訪れることが多いんですが、ここで息抜きしてから普段の世界に戻ろう、という気持ちになります。
浅沼:本当に不思議な街ですよね。和洋折衷というか。うちはしょうゆ屋で、ここの向かいは紅茶の店、隣はカレー屋とそば屋。コーヒーとチョコレートの店にフレンチレストランもあるし、ちょうちん屋もある。店主の皆さんにそれぞれ冒険譚(たん)があって、どの店も世界観が違います。
-さて、この連載では「盛岡ってなんだか居心地がいい」と感じる理由、「なんかいい」の理由を探しています。浅沼さんが「盛岡ってなんかいいな」と思うところって、どんなところでしょうか?
浅沼:私の娘もよく「盛岡ってなんかいい、葺手町ってなんかいい」ってよく言うんですよ(笑)。
それにはいろいろな要素があると思うんですが…私は「自然との近さがちょうど良いところ」だと
思います。自然と近いということは人口密度が低くて、人との距離感も程よくてちょうど良いと思います。人に疲れたなという時にも、川や山がすぐそばにあって、自然に癒やしてもらえるというか。
 矢野:今日は店の前に立派なカエデの枝が飾られていますが、これはもしかして盛岡のものですか?(※左の写真は矢野さん撮影)
矢野:今日は店の前に立派なカエデの枝が飾られていますが、これはもしかして盛岡のものですか?(※左の写真は矢野さん撮影)
浅沼:ええ。あの枝は許可をいただいて山から持ってきたものです。店先のカエデのように、手が届くからここに自然の物を持ってくることもできますが、自分から山に行くこともできて、両腕では抱えきれない自然の中へすぐに飛び込めます。人とぶつかり合った時に、相手を攻撃するのではなく、自然の中に入って1人になって、自分の中で消化する。みんなでわいわいするのも好きですが、1人になりたい時に切り替えがしやすい環境だから居心地が良いんじゃないかなと思います。
矢野:自然を「非日常」という言葉に置き換えると、盛岡は「日常と非日常」の行き来がしやすくて、それによって人との距離を程よく保ち、自分を客観的に見ることができる場所なのかもしれません。それが浅沼さんにとっての「なんかいい」につながっているんでしょうか。
浅沼:中津川の河原のような街の中にも整備されていない自然が残っていて、都市と自然の近さを絶妙なバランスで保っているんじゃないのかなと感じています。行き来がしやすいというところで、カモシカとかも街に降りてきますし。
矢野:そう言えば、私もこの前、家の近くでカモシカを見ました。「え、ここに住んでいるの?」って(笑)
浅沼:この辺にも出てきましたよ。何年前だったかな…5、6年前、夜中の2時くらいに裏手の駐車場にいたら目の前をカモシカが通って、肴町の方に走って行きました。タッタッタッて、足が速いんですよね。びっくりしました。
矢野:こんな街中にもですか? 盛岡は街中に川がいくつも通っていますから、川沿いに山から下りて、街を散策しているんですかね?
浅沼:恐らくそうだと思いますよ。カモシカみたいに生き物が居心地よく暮らしている環境が、街にいながら目に入るという近さが良いですよね。
矢野:これまでは何となく「街の中に川があっていいな」と感じていたのは、人も動物も心地よく暮らせるからなのかもしれません。
浅沼:この先、盛岡の都市化がどんどん進んでも、盛岡の「なんかいい」ところが失われてしまってはもったいないですね。
矢野:例えば、この「クラビヨリ」のように古い部分を残しながら、店を時代に合わせて変えるという精神も、盛岡の良さを残す一つの手段だなと思います。
浅沼:私の場合は、たまたまやってみたら偶然にも良かったと今実感しているところです(笑)
矢野:「なんかいい」と感じる要素が偶然にもたくさん集まっているのが今の盛岡だとしたら、何が良いのかを明らかにして、意図的に残さないといけないなと考えています。
浅沼 「なんかいい」をうまく伝える共通言語があれば面白いですよね。その時代に合う言葉で、それ以外に変えようがないという表現で、盛岡の良さを伝える言葉。盛岡弁の「いずい」みたいに、「いずいはいずいだよね」と共感しあえて、かゆいところに手が届くような言葉が、これから発明されるところかもしれませんね。
矢野 確かに。共通言語は欲しいですね。みんなで探していたら突然発明されるかも。「なんか良い」を言語化するのには必要なアイデアだと思います。「なんか良い」を考えるための核に触れたような気がします。今日はありがとうございました。
Vol.1後編はこちら
Vol.1盛岡に暮らす人<後編・伊藤隆宗さん>
盛岡の「なんかいい」話Vol.2はこちら
Vol.2 盛岡を伝える人<前編・山影峻矢さん>
Vol.2 盛岡を伝える人<後編・玉木春香さん、知念侑希さん>
盛岡の「なんかいい」話Vol.3はこちら
Vol.3 盛岡を考える人<前編・高橋真菜さん>
Vol.3 盛岡を考える人<後編・佐藤俊治さん>