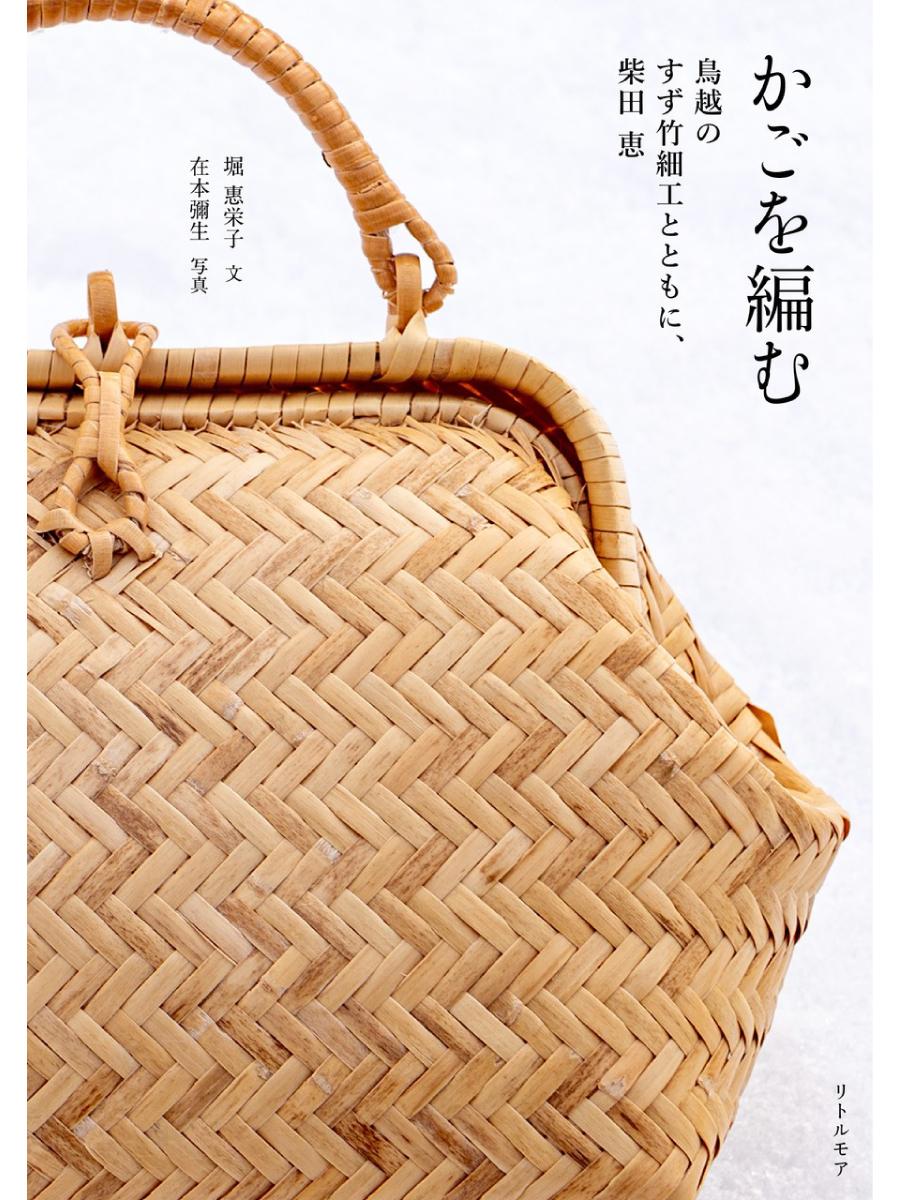盛岡ゆかりの作家・鈴木彦次郎の企画展 岩手の文化を育てた人を知って

盛岡ゆかりの作家・鈴木彦次郎の生涯をたどる企画展「鈴木彦次郎 岩手の文化の育成者」が現在、盛岡市先人記念館(盛岡市本宮)で開催されている。
今年が鈴木彦次郎の没後50年に当たることから企画された同展。鈴木は1898(明治31)年に東京で生まれ、5歳の時に父の帰郷とともに盛岡に引っ越し、18歳までを盛岡で過ごした。盛岡中学校(現盛岡第一高校)を卒業後は再び上京し、第一高等学校(現東京大学教養学)を経て、東京帝国大学に入学。太平洋戦争中の1944(昭和19)年に盛岡に疎開するまで、東京で文筆活動を続けていた。
盛岡に戻った鈴木は、現在の岩手日報の編集顧問や、県立図書館の館長、県教育委員長などを歴任。岩手日報が発行する文芸誌「北の文学」や現在も発行が続くタウン誌「街もりおか」の創刊、冬の風物詩として親しまれている「盛岡文士劇」の立ち上げにも携わっている。
担当学芸員の坂本志野さんは「彦次郎さんは岩手全体の文化に広く関わり、本人の名前よりも、本人がした事や作った物が後世に知られる人物の一人。今を生きる市民・県民にもなじみのある事物に関わっていることを知ってもらいたい」と話す。
展示は3章構成。1章は盛岡で過ごした少年時代に触れ、父の影響で夏目漱石の小説を読んでいたエピソードなどを紹介する。2章は東京での文筆活動を取り上げ、川端康成らと共に同人誌「新思潮」第6次創刊に取り組んでいたことなどを紹介。同章の後半では、大学卒業後の本格的な文筆活動に触れ、鈴木が相撲好きだったことや、相撲小説を書いていた当時を振り返って「相撲小説家のレッテルを張られてしまい、書きたいものを書かせてもらえない」と語ったことなどを取り上げている。
3章は岩手の文化の育成者と題し、盛岡に戻った後の鈴木の功績と活躍を取り上げる。「北の文学」や「街もりおか」の第1号や、明治期の盛岡の出来事などを題材にした小説「巷説(こうせつ)城下町」の原稿、本人のノートや手紙、写真アルバムを展示。戦後は入館者が少なく「内丸の化物屋敷」と呼ばれるほど荒れ果てていた県立図書館の館長を引き受けた際には、認知度向上を目指し、県内各地を巡って本の貸し出しをしていたことなどを紹介する。アルバムには、盛岡文士劇の舞台に立つ姿を撮影した写真も残っている。
同展の目玉資料の一つが、IBC岩手放送の協力による鈴木が出演するラジオ放送の音声やテレビ映像。「盛岡の先人のうち、声や映像が残っている人は貴重」と坂本さん。「さまざまな資料やエピソードからは、彦次郎さんが岩手の文化を盛り上げるため、いろいろなことに取り組んでいたことが読み取れる。みんなのためにと動いていた、器が大きい人だったと思う。彦次郎さんが育て、今も残る岩手の文化を感じてもらいたい」と呼びかける。
8月31日まで。
同記念館の開館時間は9時~17時(入館は16時30分まで)。月曜(祝日の場合は翌日)、毎月最終火曜休館。入館料は一般=300円、高校生=200円、小・中学生=100円。