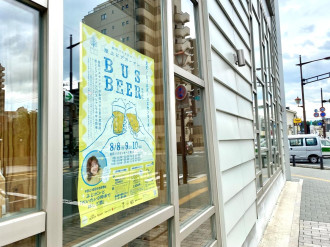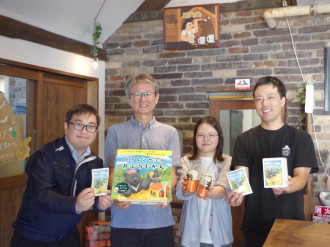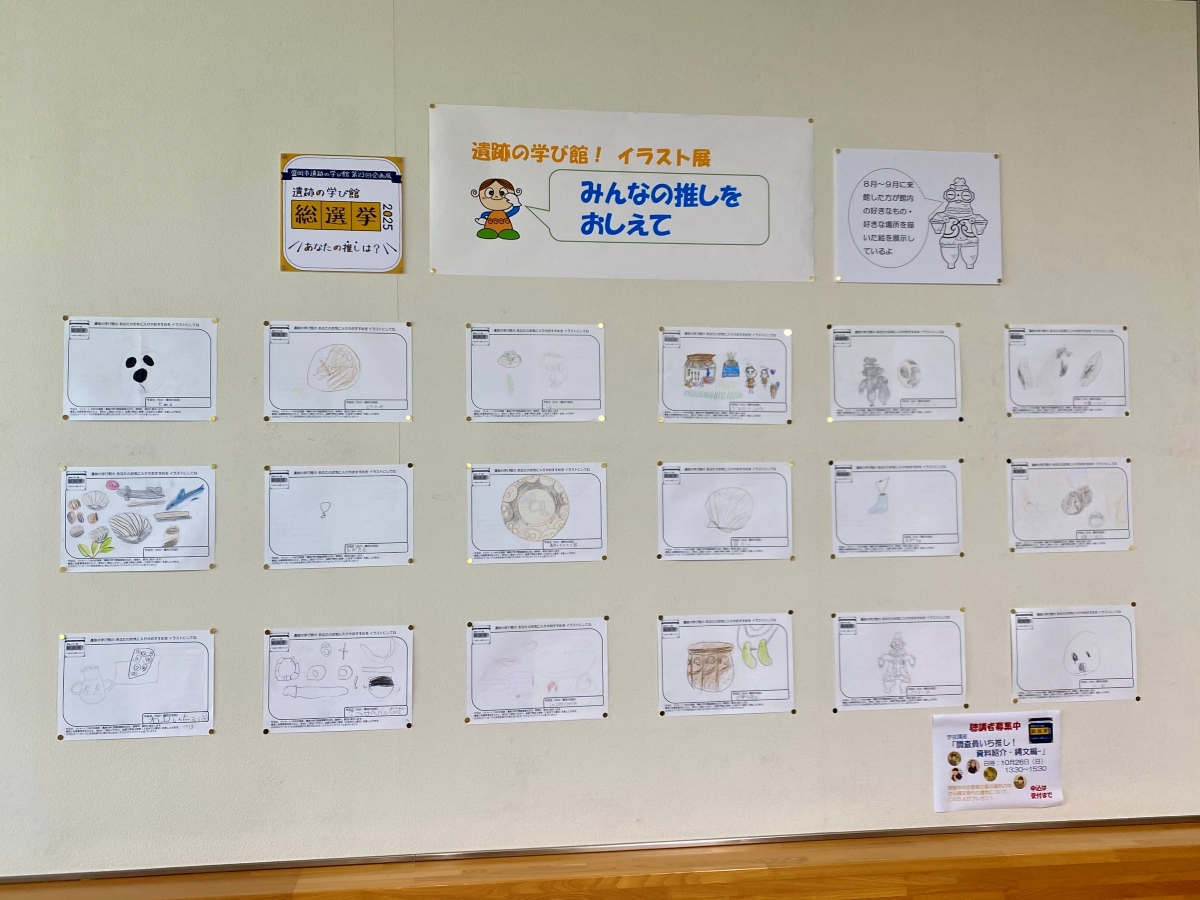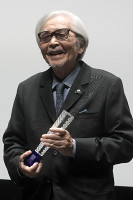岩手県立博物館で酒造りのテーマ展 南部杜氏の歴史から飲む楽しみまで

南部杜氏(とうじ)を中心に岩手での酒造りを取り上げるテーマ展「いわての酒造り~酒からSAKEへの今昔物語~」が現在、岩手県立博物館(盛岡市上田)で開催されている。
日本の「伝統的酒造り」が2024年12月にユネスコの無形文化遺産に登録されたことをきっかけに、担当者が準備を進めてきたという同展。岩手では日本三大杜氏とも呼ばれる「南部杜氏」が酒造りの技術と知識を受け継ぎ、現在も全国各地で活動している。同展では南部杜氏を中心に、岩手の酒造りの歴史や製造技術、酒文化について183点の資料で紹介する。
展示はプロローグとエピローグを含めた全7章で構成。プロローグでは無形文化遺産や伝統的酒造りとは何かについて解説し、岩手県内の酒蔵と各蔵が一押しする酒を紹介する。第1章は「酒造りの歴史」と題し、主に南部杜氏が登場する前の酒造りについて取り上げ、こうじを使った酒造りの最初の記録とされる「播磨国風土記」や、酒造の様子が描かれた「日本山海名産図会」などを展示する。
2章は「南部杜氏の酒造り」とし、南部杜氏に関する資料を紹介。盛岡藩に来た近江商人の一人・村井権兵衛が現在の紫波町で酒蔵の創業を申し出て、大阪から職人を呼び寄せ、岩手で初めて清酒の製造を行ったのが南部杜氏の始まりとされる。酒屋に関する記録や酒の飲み過ぎについて注意する記述がある盛岡藩家老の政務日誌「雑書」や、南部杜氏らが酒蔵で仕事をする時に使っていた「蔵人札」、酒造りについて記された「秘伝名酒造法」などの資料が並ぶ。
3章の「酒を造る」では、岩手県で現在使われている酒米やこうじのサンプルを展示するほか、製造工程の手順、かつて使っていた道具などを展示。4章の「酒を売る」では県内の酒造が所蔵している販促グッズや日本酒の「酒票」、量り売りに使っていた徳利、5章の「くらしと酒」では、酒文化の中で生まれたユニークな杯や酒だるを持った土人形といった資料を紹介する。
エピローグは「いわての酒造りのこれから」として、現役の南部杜氏のコメントを掲示。現代の角打ちを再現したエリアでは2023年に惜しまれながら閉店した老舗酒店「平興商店」にまつわる資料が並ぶ。
今回の展示を担当する同館の戸根貴之さんは「伝統的酒造りや南部杜氏という言葉を知っていても、実際の酒造りを知らないという人もいると思う。現代でも想像以上に人の手で受け継がれてきた技術が使われ、それを次につなげるために頑張っている杜氏の皆さんがいる。酒造りの奥深さを知り、『なんだかお酒が飲みたくなったな』と思ってもらえたら」と話す。
開館時間は9時30分~16時30分(最終入館は16時)。月曜休館(祝休日の場合は翌日)。入館料は一般=350円、学生=160円、高校生以下無料。