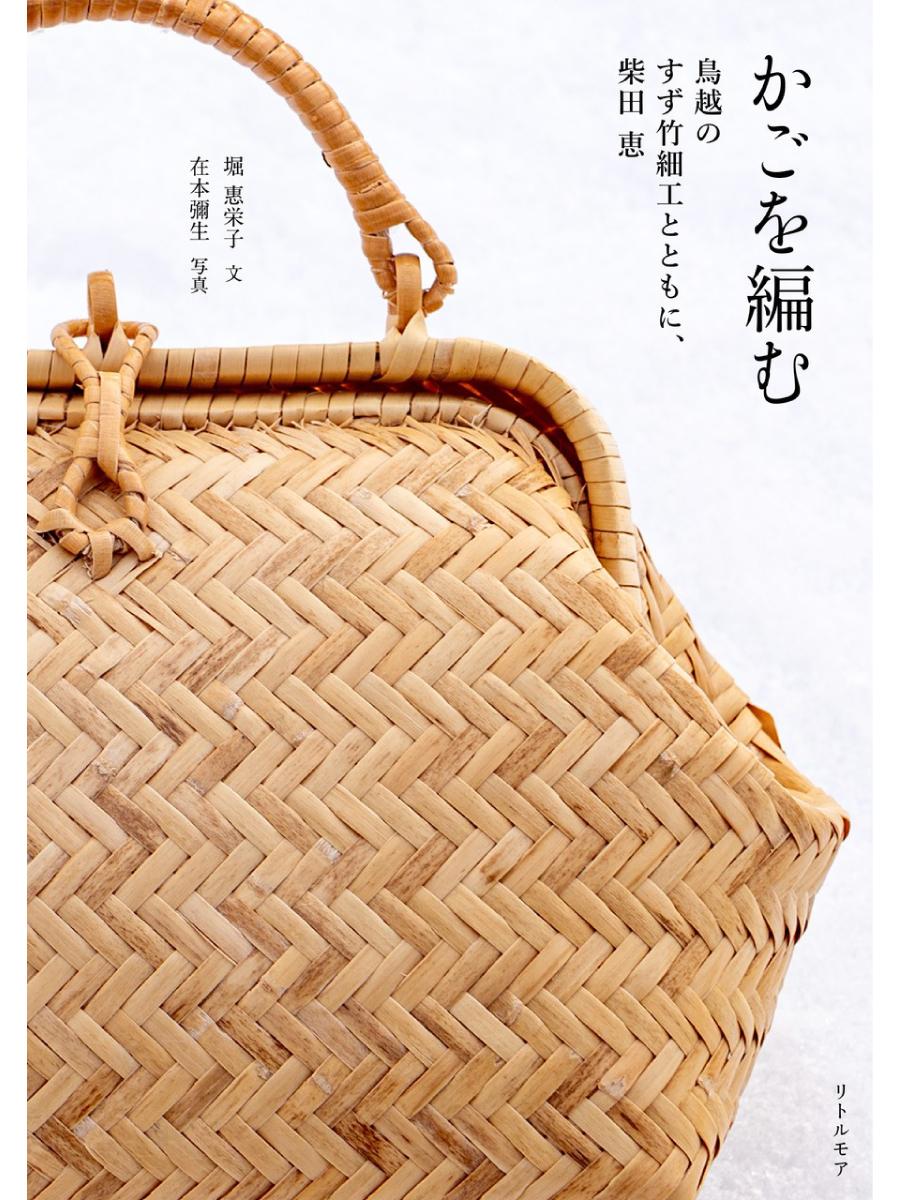岩手県立博物館で星と宇宙の企画展 岩手の歴史を中心に、国宝も来県

宇宙と星がテーマの企画展「星にねがいを-宇宙(そら)といわての年代記-」が現在、岩手県立博物館(盛岡市上田)で開かれている。
水沢緯度観測所で使われていた「眼視天頂儀」。200キロ近い重さがある
国立天文台水沢(奥州市)や、「銀河鉄道の夜」の作者・宮沢賢治、国際リニアコライダー(ILC)の誘致など、岩手とつながりが深い宇宙と星に焦点を当てる同展。岩手県域で展開した宇宙にまつわる歴史をたどり、現在県内で取り組まれている宇宙に関する挑戦などを約140点の資料で紹介する。
展示は1章~5章に序章と終章を加えた7部構成。序章では宮沢賢治の「星めぐりの歌」と天文写真を組み合わせた同店のコンセプト映像を上映する。1章は「星をまつる」と題し、祈りや信仰の対象だった星について紹介。2章の「星をまとう」では、星をかたどった家紋を身に着けていた中世の武士たちに触れ、甲冑(かっちゅう)や刀を展示する。担当学芸員の目時和哉さんは「南部家の家紋にも、鶴と一緒に星をかたどった『九曜紋』が描かれている。これは、当主が鶴と星が降りてくる夢を見たからという説がある」と話す。
3章「星をはかる」と4章「星にせまる」では、近世の天文学の発展から水沢に国立天文台ができるまでの近代の歴史を取り上げる。3章では、初めて実測による日本地図を完成させた人物として知られる伊能忠敬と岩手にまつわる資料も展示。国宝に指定されている伊能が測量に使ったとされる道具や、伊能が現在の釜石市唐丹で測量を行ったことを記念して地元の天文学者が設置した「星座石」のレプリカなどが並ぶ。
4章は国立天文台水沢の前身となった緯度観測所の設立に取り組んだ田中館愛橘や同観測所の初代所長・木村栄(ひさし)と、観測所設立までの道のりなどに触れ、観測に使っていた「眼視天頂儀」や「Z項論文」などを展示する。
5章は銀河鉄道の夜を中心に宮沢賢治と宇宙の関わりを紹介。今年が戦後80年に当たることから、同章の裏テーマを「戦争」とし、空襲を受けた夜の天体観測記録や終戦の日の気象記録も並べる。終章では現在の岩手と宇宙に関する最新トピックに触れ、県内企業が開発に関わる宇宙実験装置や花巻市で取り組む宇宙をテーマにした町おこしなどを紹介する。
目時さんは「宇宙と星は私たちにとって普遍的なテーマであり、昔は祈りの対象として、現代では学問や研究の舞台として、巡り巡って形を変えて、人の営みに関わっている。人と宇宙、そして岩手にどんなつながりがあるのか興味を持ってもらえれば」と話す。
開館時間は9時30分~16時30分(最終入館は16時)。入館料は一般=350円、学生=160円、高校生以下無料。期間中の休館日は7月7日、14日、22日。8月17日まで。